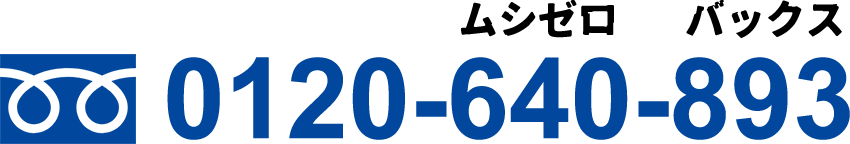お役立ち情報
お問い合わせ
ネズミの駆除!業者に依頼できる駆除作業と個人ができる予防策
この記事を書いた人:坂田 和徳
![]()
この道34 年で施工実績30,000 件以上の職人社長!
ゴキブリ・シロアリ・ネズミ駆除の専門家。
徹底的な調査とヒアリングによって他業者様には難しい案件も多数請負。
害虫駆除に加え経営・集客に関するアドバイスも可能。
こんにちは。バックスの坂田です。
屋根裏でコソコソと音がする…、ネズミが走っているのを目撃してしまった…
ネズミにはダニやノミといった外部寄生虫や条虫、回虫などの内部寄生虫などが寄生しており、深刻な感染症を引き起こすなど、人に被害を与える可能性があります。さらに家具や壁などをかじったり、電気ケーブルなどをかじって火事を引き起こしたりするため、早急に駆除しなければなりません。
そこで今回は、ネズミの特徴と被害から、個人でもできる予防・駆除方法、業者に依頼できる駆除作業に至るまで、徹底的にご紹介します!
家に出現するネズミの特徴と被害
ネズミの特徴
ネズミを駆除するためには、まずはその特徴を知って、2次元と3次元の両方で対応する必要があります。
2次元とは一般的な対応で、3次元とは上下異動を考慮した対応が必要なケースです。
①クマネズミ
運動能力が1番優れていて、警戒心も強く、駆除は難しく業者も手を焼く。
しっぽを使いながらの綱渡りが得意。
家でいえば電線類からいきなり屋根の上に来るので、どこからでも家には侵入してくる。
3次元的対応が求められる。
②ドブネズミ
ドブネズミといわれるくらいなので、普段は、下水や地面の中に生息している。
運動能力は、クマネズミに比べると相当劣るが、齧る能力は、クマネズミの何倍も優れている。鉄類で封鎖した箇所でも、齧ることが可能な場合は、齧られて突破されてしまう。
2次元的対応で良かった種だが、名古屋市内の市街地では、運動能力も優れている種が生き残り、近年は、天井裏に当たり前に上るようになってしまい、3次元的対応が求められるようになった。
③ハツカネズミ
他の2種に比べると、生息は田畑がある農村部に限定される。
大きさも小さくおとなしい種ではある。
他の2種に比べると、体液が少ないため、死んだ場合でも多少悪臭はするもののウジが湧くことはあまり無い。
この種も2次元的対応で良かった種だが、運動能力の高まりと、壁の中にグラスウールの断熱材を使用することにより、天井裏に上れるようになり、壁の中や天井裏の断熱材に巣を作ることが多くなってきており、こちらも3次元的対応が求められるようになった。
日本の家に出現するネズミのほとんどは「クマネズミ」という種類です。この「クマネズミ」の特徴について、もう少し詳しくご紹介します。
クマネズミの特徴
体長:10〜22センチメートル
体重:100〜200グラム
・警戒心が強い
・乾燥に強い
・寒さに弱い
・夜行性である
・ほとんどの環境に適応できる
・上下への移動や綱渡りが得意
・泳ぎは苦手
・高所を好む(マンションの2階以上でも住み着く)
・臆病で神経質なため、行動範囲が決まっている
・何でも食べる
・貯食性がある
・毒代謝能力が高く、殺鼠剤がきかない個体がある(スーパーラット)
・小さな穴(1.5cmほど)なら簡単に通り抜けられる
ネズミの被害
ネズミの被害には、食糧を食べられたり、家具や壁などかじられたりする他、ダニやノミといった外部寄生虫や条虫、回虫などの内部寄生虫などが寄生しており、深刻な感染症を引き起こすなど、人に被害を与える可能性もあります。
このように様々な被害がありますが、私が最も大きな被害だと考えるのは「火事」です。ネズミが電気ケーブルなどをかじって、そこに尿をかけ、ショートして火災が発生する危険性があります。大型店舗や工場などにおいては、キュービクルという高圧電力を扱う受変電設備にネズミが侵入するケースも多いです。受変電設備内でネズミが感電して停電が発生したり、ショートして火災が発生したりということもあります。このような命に関わる被害も引き起こすため、ネズミを発見したり、ネズミの存在が疑わしい場合は、できるだけ早く対策をとる必要があります。
ネズミを見つける以外にも、小さな黒い糞や尿の跡、家具や壁、床、柱に体の汚れが付着した黒い線(ラットサイン)が残っていたり、屋根裏でゴソゴソと音がしたりする場合は、ネズミの被害が広がっている可能性があります。
ネズミを発見した場合の応急処置の手順
ネズミを発見してしまった場合の対処法をご紹介します。
ネズミ駆除剤(殺鼠剤)
ネズミ駆除剤(殺鼠剤)は、ネズミに食べさせることで駆除をするための薬剤です。効果が高いものも増えており、ネズミの駆除グッズの中でも、特に欠かせないものといえます。他に、煙のタイプもあります。
ネズミ駆除剤(殺鼠剤)の使い方のポイント
ネットなどでお勧めの方法として紹介されていることも多い「ネズミの餌場に仕掛ける」「複数箇所に仕掛ける」という方法は、あまり効果的とはいえません。ネズミの駆除には、以下の2つのポイントを抑えましょう。
・天井裏が最大のポイント
特にクマネズミは、①暖かくて②暗くて③乾いている場所を好みます。ホームポジションがここになり、警戒心が一番薄れている場所です。よって、ここに設置することが、一番効果が上がるのです。
・一度置いたら1週間は動かさない
餌型の駆除剤を設置してすぐに食べている様子がなくても、1週間は動かさないようにしましょう。ネズミは警戒心が強いので、見慣れないものはすぐに食べません。餌の存在に慣れた頃に食べるようになります。
粘着シート
その名の通り、粘着質のシートを設置してネズミを捕獲します。
設置した場所に、隙間なく設置するのがポイントです。ピンポイントに設置したり、隙間があったりすると、ネズミを捕獲することは難しいです。粘着シートを使用する場合は、多少費用が嵩んでも広く設置した方が効果的といえます。
また、ネズミを引き寄せる成分が含まれたシートを選ぶと、より高い効果が見込めます。
ネズミ取りカゴ
筒の床部分に設置してある板をネズミが踏むと扉が閉まり捕獲できる踏板式と、餌でおびき寄せ、ネズミが餌を取ると重みがなくなった反動で扉が閉まる捕獲カゴ式があります。
ラットサインを探して設置しますが、置いてすぐには警戒して近づかないため、設置してある程度時間が経ってから仕掛けを作動させると捕獲できる可能性が高まります。物陰に置いたり、新聞紙をかけたりして、目立たないように設置することもポイントです。とはいえ、実際のところ警戒心が強いネズミを、カゴを使って捕獲するのは非常に難しいです。
超音波装置
超音波装置はネズミが嫌いな周波数帯の音を出すことができます。
しかし、市販の超音波装置は精度があまりよくなかったり、ネズミが音に慣れてしまったりして、あまり長期的な効果がない場合も多いです。
ネズミ駆除剤と粘着シートやネズミ取りカゴを併用することをオススメします。
殺鼠剤を食べたネズミは体に異変が生じるため警戒心が低下します。そのため、殺鼠剤の周りにネズミ取りの罠を仕掛けておくことで、かかりやすくなるからです。
業者が行う対策(アフターサービスまで解説)
業者に依頼した場合の対策についてご紹介します。
①ネズミの生息場所・侵入ルートを特定する調査
まずは建物を見て、ネズミの生息場所や侵入ルートを特定します。
ゴキブリのような小さな生物は、完全に侵入経路を防ぐことは難しいですが、ネズミの場合には、侵入できるルートを全て探し出すことが非常に重要なポイントになります。
エアコンの取り付け部分の穴、屋根の隙間、シャッターの隙間など、ありとあらゆる隙間をチェックしていきます。
ネズミの種類によって最適な対策は異なりますので、ネズミの種類も特定します。
②殺鼠剤や粘着シートを使用した駆除
殺鼠剤や粘着シートを使ってネズミを駆除します。最適な場所に薬剤や粘着シートを設置することで効率的に駆除を行います。
その他、忌避剤をまいてネズミを家から追い出す方法もあります。
バックスでは、長年の経験と知識を活かして作成した独自の毒餌を使用しており、効果には絶対的な自信があります。この魔法の毒餌があるから、ネズミが確実に寄ってきて、100%の駆除ができるのです。
③消毒、清掃
ネズミの再発生を防ぐために、徹底的に清掃や消毒を行います。
もちろん、捕獲したネズミの死骸も業者側で処理します。
④侵入ルート隙間の閉塞
ネズミの防除・駆除については、この侵入ルートを塞ぐことが全てだといっても過言ではありません。今いるネズミがいなくなった後は、上流(侵入)さえ潰せば他は何もしなくて良いのです。そのため、ただネズミを捕まえるだけではなく、侵入ルートを様々な方法で塞いでいきます。
ネズミの捕獲ばかりに力を入れ、侵入ルートの閉塞を重視していない業者もありますが、それではいつまで経っても完全駆除はできません。
バックスでは、徹底的にこの侵入ルートを塞ぐことで、メンテナンスなしで日本初の5年間という長期保証を実現しています。
実は侵入ルートを断つ方法には、塞ぐ以外の方法もあるんです。
例えば、一度外に出てしまったら入ってこられなくなるような仕掛け扉や、電柱から屋根に入ってこられなくなるような鼠返しなどです。こうした仕掛けをうまく使うことで、穴を塞ぐ施工をするよりもはるかに安く侵入を防ぐことができるケースもあります。
バックスでは、このように独自の技術や長年の経験を活かした仕掛けにより、安くて確実な方法で防除・駆除を行うことができるのです。
⑤アフターフォロー
作業後1年〜5年程度の保証期間を設けている場合があります。保証期間内にネズミが発生した場合は、割引価格や無料で再施工をしてもらえるというものです。
バックスでは、防除・駆除効果に自信を持っていますので、100%防除・駆除できなかった場合には費用をいただいておりません!
自信があるからこそ、毎月、毎年のメンテナンスなし5年保証プランもご用意しております。
業者に頼んだ失敗例
せっかく業者に高いお金を出して駆除や防除を依頼したのに、完全に駆除されていなかったり、必要以上に費用をとられてしまったり、何度も再発生してしまったり…残念ながら、そんなケースをよく耳にします。
他の業者に頼んで失敗し、バックスにきてくださったお客様の事例をご紹介します。失敗例を知り、確実で無駄のないネズミ防除・駆除をしてくれる業者選びの参考にしてください。
侵入ルートを塞がず、完全駆除ができていない
ネズミ防除・駆除の失敗は、「侵入ルートを塞がず、完全駆除ができていない」がほとんどといえます。毎月何十匹のネズミを捕獲、駆除できたとしても、侵入ルートが断たれていなければ、何度でも侵入してきてしまいます。
シャッターの隙間が空いていた、壁に穴が空いていた、エアコンのダクト、ガス管や電気配線の導入口から屋内に侵入していたなどのケースのほか、キュービクル(受変電設備)のケーブルの隙間から侵入することもあります。キュービクルへの侵入は、火事のリスクが高いので、特に注意が必要なケースといえます。
大手に毎月のメンテナンスを依頼し、キュービクルで毎月何百匹ものネズミ捕獲しているものの数が減らないことに痺れを切らしたオーナーさんから、バックスにご依頼が。このケースでは、侵入経路を塞ぎ、一度外へ出たら入ってこられない仕掛けを施し、居座るネズミは毒餌を使って駆除。完全駆除が実現し、大変喜んでいただけました。
毎月のメンテナンスで費用ばかり嵩む
侵入ルートを塞ぐ施工は費用が高くなることが多く、見積もり段階で断られるケースもあることから、一回の支払いが少ない毎月のメンテナンスを提案する業者も多いです。もしくは、完全駆除するだけの技術がないケースもあります。
その上、実際のところ完全に侵入ルートを塞いでしまうとネズミは再発生しなくなるので、害獣駆除業者としては儲からなくなってしまうため、毎月のメンテナンスの方が業者にとってはありがたいという側面もあるのです。
しかし、侵入ルートを塞がずに毎月のメンテナンスを行っても、それが永遠に続くだけ…。費用ばかりが嵩んで、根本的な解決につながりません。
バックスでは、長年蓄積したノウハウにより、最小コストでの完全駆除を実現しています。
おおよその見積もり
どのような施工を依頼するか、被害状況、家の広さなどによって金額は様々です。
1〜2匹のネズミを駆除するだけで侵入防止策なども不要であれば、1〜2万円で済む場合もありますが、根本的な解決にはならないのでオススメはできません。
大手で毎月のメンテナンスを依頼した場合、月額2万円(年間24万円)程度が相場です。侵入防止策まで実施した場合は、初回の施工で40万〜50万円程度かかるケースもあります。
保証期間によっても金額が異なります。また、同じ長期保証であっても、アフターフォローの内容によって金額が異なります。ただ餌や粘着トラップを取り替えるだけなのか、改めて調査をして完全駆除をしてくれるのか、内容をしっかり確認しましょう。
バックスでは、本当に必要な施工を高い技術で無駄なく行っております。
毒餌による駆除のみ
6ヶ月保証 ¥70,000~
毒餌による駆除+侵入防止対策予防
1年保証 ¥120,000~
毒餌による駆除+侵入防止対策予防
5年保証 ¥150,000~
高ければ良い、安ければ良いわけではありません。施工内容や実績、保証内容をよく比較した上で、信頼のできる業者に依頼してくださいね。
個人でもできる予防策
業者が行うような対策を個人で行うことは難しいですが、できることがないわけではありません。個人でもできる予防策をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください!
ネズミを効果的に防除・駆除するためには、侵入経路を確認することが重要です。また、一度駆除をしたと思っても、侵入経路に対する対策が取られていなければ、またネズミが住み着いてしまうことにもなりかねませんよね。侵入してしまうと、ネズミは大抵の環境に適応してしまうため、まずは侵入させないことが必要なのです。
ここでは、ネズミの侵入経路の例と、その見つけ方をご紹介します。
ネズミの侵入経路
1.5〜2cmでも隙間があればネズミは侵入できてしまうため、ほんの小さな隙間や穴からも侵入する可能性があります。
・外壁のひび割れや穴
・床下の通風口
・換気扇
・ひさしの下の隙間
・屋根の下にある通気口
・エアコンの導入部分
・エアコンの室外機
・基礎と建物の隙間
・電線の導入部分
・戸袋(雨戸を収める部分)の隙間
・地面の穴
・各種配管と壁貫通部分の隙間
・排水パイプ
他にも、クマネズミは2階の空いている窓から侵入することがあります。
換気の際などにも注意が必要です。
ネズミの侵入経路の見つけ方
ネズミの侵入経路を見つけるには、ラットサイン(ネズミの通り道)を探します。
ネズミが通ったあとは家具や壁、床、柱に体の汚れが付着した黒い線が残っていたりします。壁に沿って走る習性があるため、壁や部屋の隅にラットサインがあることが多いです。
侵入経路の塞ぎ方
ネズミは硬く鋭い前歯でなんでもかじりつきます。そのため、小さな穴を見つけると、穴を広げて家や倉庫の中へ侵入してしまうのです。ガムテープや段ボールで侵入経路を塞ぐ程度では、また自分でかじって隙間を広げてしまう可能性があるので、かじって破られないような対策も必要です。
・隙間パテで埋める
隙間パテの中には、ネズミがかじることができない強度を持ったものや、ネズミの嫌いな匂いや成分が含まれた、ネズミ専用のものがあります。できるだけ、そうした商品を利用するようにしましょう。
・金網を設置する
通風口などはパテで覆ってしまうわけにはいきません。ネズミがかじることができない金網を設置するようにしましょう。金網の他に、金属タワシで防ぐこともできます。
・ネズミの嫌いな匂いで追い払う
侵入経路を塞ぐ以外の方法として、ネズミの嫌いなニオイで追い払う方法があります。
ネズミは、ミントやカモミール、ハッカといったハーブ系の匂い、ユリやワサビなどの強い匂い、猫や蛇などの天敵のニオイは苦手だといわれています。
庭にハーブを植えたり、ニオイのついたスプレーを住処に吹きかけたり、ネズミの天敵である猫を飼ったりすることもネズミ対策の一つです。
しかし、ネズミは屋根裏を住処にすることが多く、庭のハーブや飼い猫のニオイが届きにくいですし、スプレーの効果も一時的であることが多いです。
まとめ
ネズミの駆除は長期戦です。非常に警戒心が強いため、市販のグッズなどを設置したら気長に根気よく待つようにしましょう。
それでも効果が出ない、さらにひどくなった、時間が経過するとまた発生する等の現象が起きる場合は、業者に相談しましょう。侵入経路をしっかり塞いでもらえば、長期間にわたってネズミの発生を防ぐことができますよ。